皆さん、日本では男色が古くから浸透していたことご存じでしょうか。意外かもしれませんが、日本の男色文化は何と古代ギリシャのレベルにまで匹敵すると言われており、宗教的に監視されていたヨーロッパや中国とは異なりかなり大っぴらに男色が展開されていたのです。というのも誰もが知るあの戦国武将も男色を楽しんでいただとか。一体日本ではどのように男色が展開されていったのでしょうか。今回はそんな意外と知らない日本の男色文化を見ていきます。
日本の男色の歴史
それでは日本における男色がいつからどのように浸透していったのか見ていきましょう。日本において「男色」(男性同士の性的関係)は、古代から存在していました。鎌倉時代以前の男色の記録は特権階級に限られていましたが、室町時代以降には庶民の間にも広がっていることが記録されています。これらの記録が少ないのは、当時の日本社会では男色が自然なことであり、特別視されることがなかったからと考えられています。そのため、男色がどれだけ当たり前のものであったかは容易に想像できます。
男色の起源

日本の男色文化がいつから始まったのかについては諸説あります。江戸時代前期に井原西鶴が記した『男色大鏡』には、当時男神とされていた天照大神が日千麿命(ひのちまろのみこと)を男色の関係で愛していたと記載されています。また、西鶴は、伊耶那岐命(イザナギノミコト)と伊耶那美命(イザナミノミコト)の夫婦の神が誕生する前は、男神ばかりだったので男色を楽しんでいたと主張しています。これに従うと、日本の男色の歴史は神代の時代にまで遡ることになります。
男色に関する最古の記述は、720年(養老4年)成立の『日本書紀』に見られます。小竹祝(しののはふり)と天野祝(あまののはふり)の関係が発端となった「阿豆那比の罪」に関する物語がそれです。「祝」とは神主のことであり、これらの神主が男色の仲にあったとされています。彼らは「善友(うるわしきとも)」、すなわち性的行為を伴う親友であったと記されています。小竹祝が病気で亡くなった際、天野祝は後を追い、生前の希望通りに二人を合葬しました。しかし、これが神道の天津罪(あまつつみ)とされ、昼間でも暗くなったというエピソードが残っています。この話は、男色が当時から罪として認識されていたわけではなく、むしろ神主を合葬する行為が儀式的に問題視されたことを示しています。
寺院や宮中での男色の流行

『日本書紀』以降にも、『万葉集』や『源氏物語』などの有名書物に男色についての記述があります。これらの記述から、男色が当たり前に流行していたことがわかります。空海が日本に男色を持ち込んだという説もありますが、平安時代初期の空海の帰国以前から男色の記述が存在しているため、これは俗説と考えられます。しかし、空海の影響で僧侶と稚児(剃髪前の少年修行僧)の間の男色が流行したことは確かです。
奈良時代の僧侶は『四分律』という仏教の経典をよく読んでいました。この経典には、性行為を戒める「婬戒(いんかい)」があり、異性・同性を問わずあらゆる性行為が禁止されていました。しかし、仏教では女性との性行為を嫌う傾向が強く、徐々に男色を許容する文化が発展していきました。稚児との性行為を、稚児を神格化する儀式「稚児灌頂(ちごかんじょう)」とすることで、性行為を禁止する仏教において男色を正当化する方法が作られました。
僧侶と稚児の関係は、『後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)』でも詠まれており、天皇の命令で編成された和歌集にも載せられるほど当たり前で許容されたものでした。また、宮中においても、貴族が美しい稚児を側に置き、枕をともにすることは珍しくありませんでした。
武士の男色文化「衆道」

武士が勢力を増していくにつれ、貴族や僧侶との交流の中で武家社会にも男色は浸透していきました。室町幕府を率い、南北朝を統一した足利義満は、貴族や僧侶から男色を含むあらゆる文化を積極的に取り入れ、後に流行する武士特有の男色文化「衆道」の礎を築いたとされています。
「衆道」とは、主君と小姓(将軍のそばに仕える若者)との間での男色の契りのことを指し、肉体的だけでなく精神的な結びつきを特に重視しました。男色は絶対服従の関係や絆を築く一種の儀式と認識されていました。「衆道」の予兆は、源平合戦のあった平安時代末期にも見られましたが、衆道文化が花開いたのは戦国時代です。
多くの武士たちが妻子を残して戦に出かけた当時、女性のいない環境の中で男性を性的対象として見ることは容易に想像できます。「桂男の術」と呼ばれるスパイ任務を遂行する際、美少年の色仕掛けに嵌って殺された武将も多かったと伝えられています。
庶民も受け入れた男色の風習
室町時代には、庶民の間でも男色が広まりました。庶民階級が楽しんだ能楽「手猿楽」では、美少年を使った「稚児猿楽」が生まれ、酒席で多くの人を楽しませ、一夜を共に過ごすこともありました。
宣教師フランシスコ・ザビエルは、一神教と一夫一妻制、そして男色の罪を日本人に説明することの難しさを本国への手紙で嘆いています。日本では男色が僧侶を含むあらゆる階層で当たり前のものとされていたのです。
江戸時代においても、男色は女性を愛するのと同じように普通に扱われていました。江戸時代には、若衆歌舞伎が舞台後の酒宴で売春行為を始めたことから、陰間と呼ばれる男娼が登場しました。彼らは、僧侶や武士だけでなく農民や職人などの多くの庶民を相手にしていました。江戸時代に来日した朝鮮通信使・申維翰(しんゆはん)は、著書『海游録』で男娼の色気は時に女性を上回ると記しています。
欧米の影響でタブーとなった男色
江戸以前の日本における男色は、社会的に自由であり、男同士の性的関係が「倒錯」や性的異常、病気、「変態」として差別されることはありませんでした。しかし、明治以降、近代化の過程で西洋の性科学や同性愛を罪悪視する価値観の影響を受け、日本でも同性愛は「変態」や性的「倒錯」として周縁化されていきました。例えば、同性愛関係にあった男性が法的に処罰されることもありました。これにより、男色は次第にタブー視されるようになったのです。
明治時代でも、当初は女性に溺れるよりは男色の方が良いとされ、「ストイックさ」を追求する学生の間で男色文化が残っていました。しかし、1873年(明治6年)には男性同士の性行為を罪とする「鶏姦(けいかん)罪」が規定されました。当時の日本は西洋の列強国に追いつくことを目標としていたため、欧米諸国でタブーとされる男色を容認するわけにはいかなかったのです。この「鶏姦罪」は1882年(明治15年)には廃止されましたが、明治後期には男色を悪とする考えが強まりました。そして大正時代に入ると、西洋的な考え方がさらに浸透し、ついには男色が「病気」として扱われるようになってしまいました。
男色で有名な偉人
日本でこのような歴史をたどってきたことから男色が世間に浸透していました。では一体どんな人が実際に男色だったのでしょうか。今回はみんなが知っている有名人が男色であったことも紹介していきます。中にはその人の男色がきっかけであの有名なシステムが誕生したことも。。
藤原頼長

藤原道長の後を継ぎ、摂関政治の最盛期を謳歌した藤原頼通は、その男色の嗜好でも知られています。鎌倉時代に成立した日本最古の舞楽書『教訓抄』には、頼通が別荘である宇治平等院で仏教行事を行った際、美少年峯丸の舞に心を奪われた様子が描かれています。
また、鎌倉初期の説話集『古事談』には、頼通の家来であった源長季が頼通の男色の相手であったと記されています。このように、頼通の男色の趣味は広く知られていたのです。
さらに、頼通の孫にあたる藤原頼長も男色の趣味を持っていました。保元の乱で受けた傷が原因で亡くなった頼長は、7人もの貴族と男色関係にあったと伝えられています。当時の貴族は日記を残す風習がありましたが、頼長は宮中儀式だけでなく自身のプライベートについても赤裸々に綴っています。
頼長の日記『台記』には、彼が男色で感じた快感や少年たちへの恋慕の情が詳細に記されています。特に「倶(とも)に精を漏らす」つまり「一緒に射精する」ことの喜びを綴った直接的な表現には驚かされます。このように、頼長の男色遍歴は当時の貴族社会の一端を垣間見ることができる貴重な資料となっています。
織田信長

日本史上、最も有名な人物の一人である織田信長も、男色の経験があったと言われています。特に有名な相手が森蘭丸です。森蘭丸は幼少期から端正な顔立ちで知られ、信長に非常に気に入られていました。信長は蘭丸に身の回りの世話をさせ、秘書的な役割も担わせていたといいます。
さらに、信長には前田利家とも男色関係があったのではないかという説もあります。このように、信長の男色関係は複数の人物との間で語られており、彼の私生活の一面として興味深いものとなっています。
武田信玄

戦国時代において、実力No.1の武士として知られる武田信玄も男色の経験があったとされています。彼の有名な相手は高坂昌信です。高坂昌信は幼少期から容姿端麗で、信玄は彼に非常に思いを寄せていました。
ある時、信玄が他の人に手を出した際には、そのことを釈明する手紙を高坂昌信に送ったと言われています。この手紙はまるでラブレターのような内容だったと伝えられています。このエピソードからも、信玄と高坂昌信の関係の深さがうかがえます。
伊達政宗

「独眼竜」の名で知られる戦国武将、伊達政宗も男色の経験があったと言われています。彼の相手として有名なのが片倉重長です。戦国末期に活躍した政宗と重長の間には、大坂の陣出陣前の逸話が残されています。
重長にとって初陣となるこの戦いで、彼は片倉家の名を汚さぬよう先陣を任せてほしいと政宗に頼みました。これに対し、政宗は涙を流しながら「お前以外の誰にも先陣をやらせない」と承諾しました。この逸話からも、政宗と重長の深い絆と愛情がうかがえます。
徳川家康と徳川家光

戦国時代を制し、天下人となった徳川家康にも男色のエピソードがあります。家康は本来年上の女性を好んでいましたが、『甲陽軍鑑』によれば、忠臣の井伊直政の美しさに魅了され、関係を持ったとされています。
また、江戸幕府の三代将軍・徳川家光には、元服前の苦い経験から女性を受け付けなくなったという話があります。しかし、将軍として子孫を残すことは重要な務めでした。これを心配した権力者の春日局は、家光の側室に小姓姿をさせて彼の興味を引こうとしたと伝えられています。この家光の男色嗜好が、後に大奥の誕生のきっかけになったとも言われています。
松尾芭蕉

有名な俳人である松尾芭蕉は、弟子たちと一緒に旅をすることが多く、その中の二人とは恋仲であったと言われています。『奥の細道』がよく知られていますが、芭蕉の紀行文『笈の小文』には、杜国(とこく)と越人(えつじん)という二人の愛弟子との旅について記されています。
越人との旅では、「寒けれど二人寝る夜ぞ頼もしき」というロマンチックな句を詠んでおり、杜国と一緒にいる際も「草の枕のつれづれ二人語り慰みて」と詠むなど、二人の関係がわかる句を残しています。これらの句からは、愛する人との旅行を楽しんでいる芭蕉の姿が思い浮かびます。
国や地域によって考え方は異なりますが、時代によっても価値観は大きく変わります。同じ日本でも、かつて当たり前だったことがタブー視されるようになったり、その逆もあります。日本における男色の歴史を知ると、「当たり前」とは何かについて改めて考えさせられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回見てきたように日本の男色の歴史は、古代から近代に至るまで非常に多様で深い背景を持っています。古代や中世には、男色は特権階級から庶民に至るまで広く受け入れられ、自然なものとして社会に溶け込んでいました。寺院や宮中、武家社会での男色は文化や儀式の一部として存在し、多くの文献や物語にその痕跡が残されています。しかし、明治以降の西洋化と近代化の過程で、西洋の性科学や同性愛を罪悪視する価値観が日本にも浸透し、男色は「変態」や性的「倒錯」として周縁化されていきました。
本サイトでは日本の男色以外にも様々な面白い日本の歴史や文化を紹介しています。興味ある方はぜひ他の記事も読んでいただけると嬉しいです!

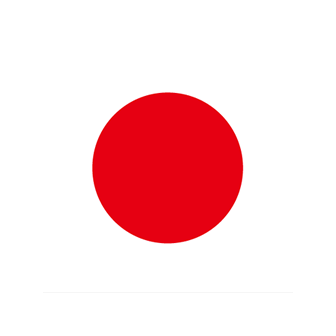


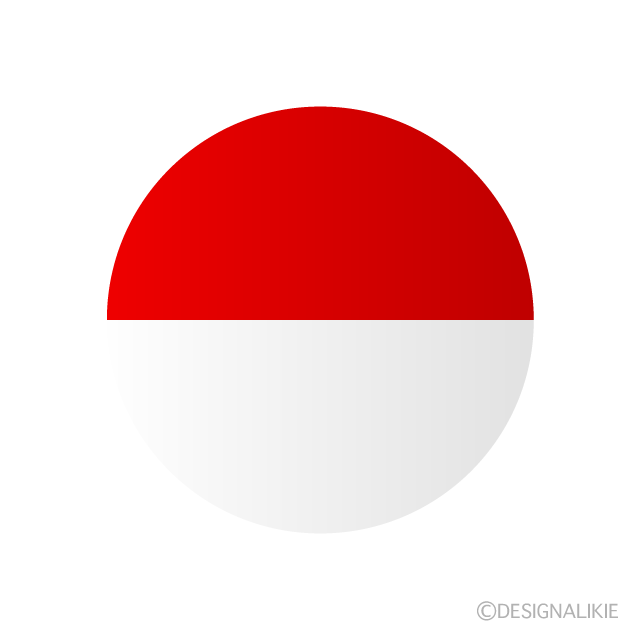











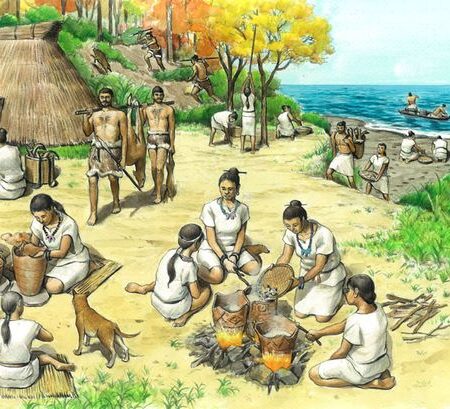
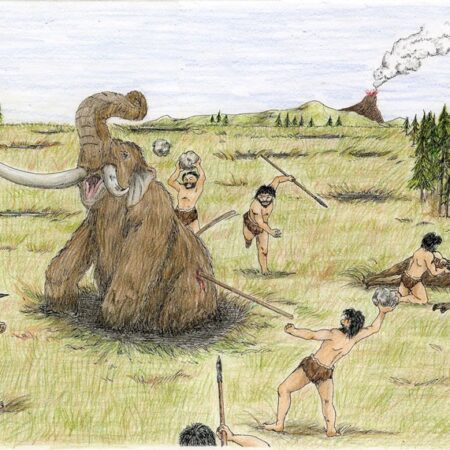

















コメント