皆さん、カラスと聞いてどんなイメージを抱きますでしょうか?夜の街を歩いていると、カラスの鳴き声が響く。その姿は不気味さを感じさせることもあれば、どこか神秘的な魅力を放つこともあります。日本には古くからカラスにまつわる迷信が数多く存在し、その中には良いイメージを持つものもあれば、悪いイメージを持つものもあります。今回は、そんなカラスにまつわる迷信の両面を探ってみましょう。
カラスが不吉の象徴だと思われている理由
それではまずはカラスが不吉の象徴である迷信を見ていきましょう。いくつかは聞いたことがある内容かもしれません。
「カラスが鳴くと人が亡くなる」という迷信

誰もが一度は聞いたことがある迷信ですが、これはどういった背景で生まれた迷信なのでしょうか。「カラスが鳴くと人が死ぬ」という迷信の背景には、日本の古い葬儀習慣があります。昔の日本では、火葬ではなく土葬が一般的でした。亡くなった人が地中で空腹にならないようにと、埋葬の際に墓に料理を供える習慣がありました。しかし、その料理の匂いに引き寄せられたカラスが墓場に集まり、供え物を食べるようになりました。
カラスは非常に知能が高く、墓場に行けば食べ物が手に入ることを学びました。その結果、墓場には大量のカラスが集まり、カラスの鳴き声が響き渡るようになりました。この現象が、人々に不吉な印象を与え、「カラスが鳴くと人が死ぬ」という迷信が生まれたと考えられています。
この迷信は、カラスが死者のための料理を食べる姿や、カラスの鳴き声が不吉であるという感覚から生まれたものです。カラスが集まることで、死の気配が感じられるようになり、その結果としてこの迷信が広まりました。
そもそもカラスに対するマイナスイメージ
誰もが一度はカラスに対して抱くマイナスのイメージがあることもカラスが不吉であるというイメージを形成していると考えられます。それもそのはず、私たちの日常生活で目にするカラスは、見た目が真っ黒で不気味に見えることが多いからです。また、カラスはゴミ袋を漁る姿がよく見られ、その行動が町の清潔さを損なうこともあります。さらに、カラスは時折攻撃的な態度を見せることがあり、人々に対して威嚇したり襲いかかることもあります。このような理由から、多くの人々はカラスに対して悪いイメージを抱いてしまうのです。
日本での「黒=悪い」というイメージ
その他には日本では「黒=悪い」とう強いイメージも根付いています。実は江戸時代までには「黒=悪い」といったイメージが形成されていなかったのですが、明治時代以降にがらりと変わりました。明治時代以降の西洋文明の影響によるものです。それまでの日本では、喪服は白や自然な生地の色が一般的でした。
しかし明治時代に入り西洋文化の影響を受ける中で、代表的な影響として喪服が次第に黒に変わっていきました。この変化とともに、黒に対するネガティブなイメージも広まっていきました。ブラック企業やブラックリストという言葉もあります。今日では、「黒=悪い」という考え方は明治時代以降に形成されたものであると言えます。
カラスは八咫烏で神の使い?

一方でカラスには良いイメージも存在します。代表的な例が八咫烏という神の使いもしたカラスです。サッカー日本代表のロゴにもなっているので、名前は知らなくとも八咫烏は見たことある方もいるかと思います。
八咫烏(やたがらす)は、日本サッカー協会のシンボルマークにもなっている特別なカラスです。このカラスは、神武東征の際に熊野から大和まで道案内をしたと伝えられており、熊野の神様のお使いとされています。古代の文献『延喜式』には「三足烏 日之精也。白兎 月之精也」と記されており、太陽の精霊としての八咫烏の姿が描かれています。
朝廷の儀式用装束や祭具に、また日本各地の祭では鉾や的に太陽と烏、月と兎が描かれるように、八咫烏は太陽の中に住む霊力を持つ鳥として尊ばれてきました。八咫烏の「咫(あた)」は、寸や尺といった長さを表す単位の一つですが、「八百万(やおよろず)」が「たくさん」を意味するのと同様に、「八咫」は「大きい」を意味しています。
現在、八咫烏は導きの神様、交通安全の神様としても崇敬されており、特に礼殿左手の御縣彦社(みあがたひこしゃ)でお祀りされています。このように八咫烏は、日本の神話や歴史に深く根付いた特別な存在であり、その霊力や導きの力が広く信仰されています。
なぜサッカー日本代表のロゴが八咫烏なのか

日本サッカーと八咫烏(ヤタガラス)の関係は、サッカーの日本への普及に大きく貢献した中村覚之助に由来しています。和歌山県出身の中村覚之助は、東京師範学校(現在の筑波大学)在学中にフットボール部を創設し、これが日本でのサッカーの始まりとされています。
中村覚之助の功績を称え、日本サッカー協会は彼にちなんだシンボルを探し求めました。そして辿り着いたのが、中村の故郷である和歌山の熊野でした。この地には、三本足のカラス「ヤタガラス」にまつわる伝承がありました。ヤタガラスは、神話において導きの神とされる特別な存在であり、その霊力や導きの力が信仰されています。また、熊野地方には古くから蹴鞠(けまり)というサッカーに似たスポーツの伝統もありました。
こうした背景から、日本サッカー協会は八咫烏をシンボルとして採用することに決めました。八咫烏は、日本サッカーの象徴として、その歴史と伝統、そして未来への道標として大切にされています。このように、八咫烏と日本サッカーは深い歴史的な結びつきを持ち、その象徴として広く認識されています。
なぜカラスで良いイメージと悪いイメージが混在するのか

古くから神話などで導きの神様として祀られ、とくに八咫烏として祀られているにも関わらず、一体になぜネガティブなイメージが定着しているのでしょう。それは明治時代以降にイメージの上乗りが生じたからかと考えられます。当時は近代化を至上命題としていたため、西洋での「黒=悪い」というイメージがそのまま定着してしまったと考えれます。また八咫烏といった神聖なイメージは日常生活で遭遇せず、街でごみを喰い漁るよくある光景が思い浮かぶ方もいらっしゃり、そういったイメージから「カラス=悪いもの」といった早期がされているのかもしれません。
海外でのカラスの見られ方

日本だけではなく、カラスは、世界で古来より様々な文化や神話において重要な役割を果たしてきました。中国では、太陽にカラスが、月にウサギが棲むとされ、それぞれが月日を象徴する「烏兎(うと)」として現れています。また、清朝のヌルハチはカラスに命を救われた逸話があり、カラスは神聖な動物として尊重されています。
アジア以外でもカラスは重要視されています。エジプトでは太陽の鳥とされ、イギリスではアーサー王が魔法で大ガラスに変身させられた伝説から、大ガラスを傷つけることは王に対する反逆行為とみなされ、不幸を招くとして尊重されています。
ギリシャ神話にもカラスは登場し、元々は白銀色で美しい声を持ち、太陽神アポロンに仕える賢い鳥でした。しかし、アポロンの妻が他の男性と仲良くしていることを告白したため、アポロンの怒りを買い、現在の黒い姿になったとされています。またケルト神話では、女神がワタリガラスの姿で登場し、その中でもバウズという女神がカラスの化身として伝えられています。
このようにカラス自体は日本でも海外でも神に使える動物として見られている傾向が強いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回カラスの迷信についてネガティブなイメージとポジティブなイメージを見てきました。元々神聖であるとされていたのに、明治時代は西洋化による「黒=悪い」という先入観が私たちの頭の中にできてしまったことが多いとみています。また海外では当たり前のようにカラスが神様として祀られています。
本サイトではカラスの迷信以外にも、様々な日本の面白い記事を書いています。もし興味ございましたら、ぜひ他の球技も見ていただけますと幸いです。


























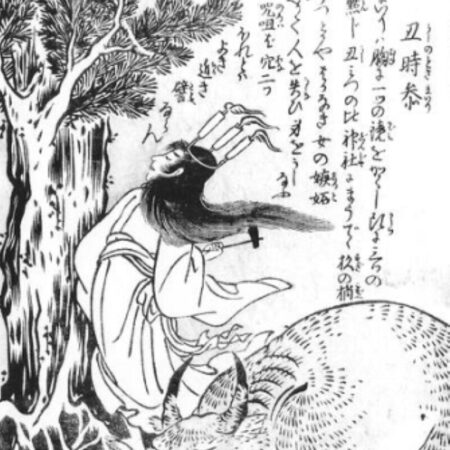
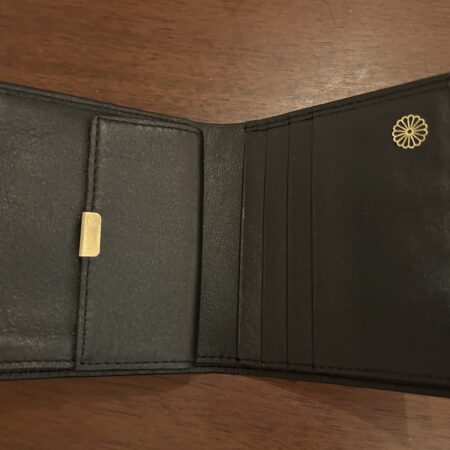






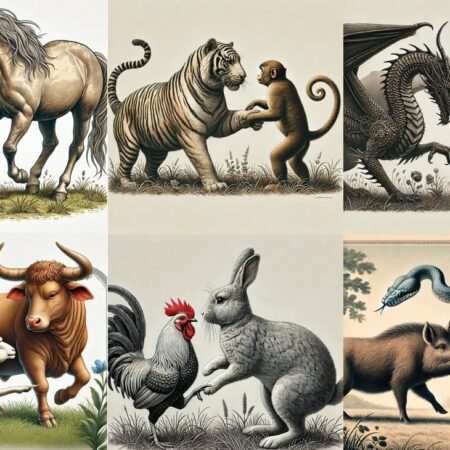

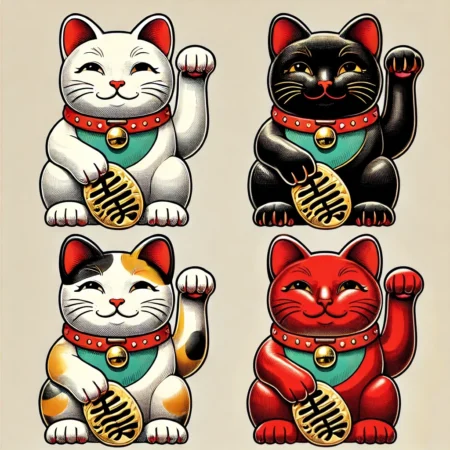
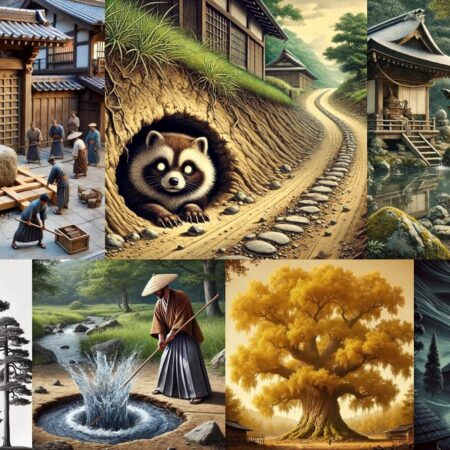
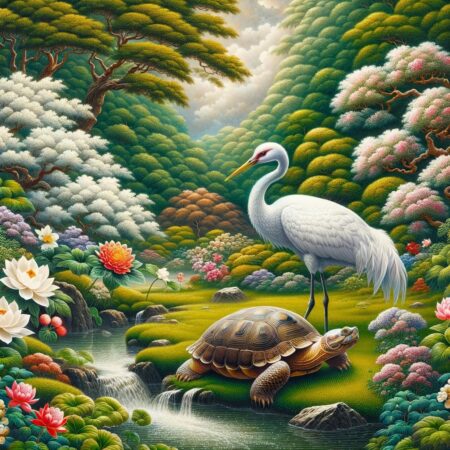
コメント